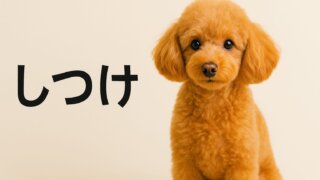- トイプードルの「おすわり」は基本中の基本。正しく教えることで飛びつきや落ち着きのなさも改善できる。
- 成功のカギは“タイミング・一貫性・愛情”。家庭全体でルールを統一することが大切。
- 覚えない・できない場合は病気やストレスの可能性も。原因を見極めたうえで適切に対応しよう。
「うちの子、なかなか“おすわり”を覚えないんです……」
そんなお悩みを抱えていませんか?
トイプードルは賢くて学習能力が高い反面、感受性が強く、しつけの仕方によっては混乱してしまうこともあります。
私自身、愛犬のトイプードルに「おすわり」を教える際、何度も失敗を繰り返しながらようやくコツをつかみました。
実体験と専門情報をもとに、誰でもできるしつけ方法をわかりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
しつけの順番に沿って記事を読む場合↓
Contents
「おすわり」はなぜ重要?その役割と効果を知ろう

- おすわりは基本指示のひとつ
- 飛びつき防止や落ち着かせる効果
- 信頼関係構築にもつながる
おすわりは基本指示のひとつ
「おすわり」は犬にとって最も基本的なコマンドの一つです。
多くのしつけがこのコマンドから始まると言われています。
なぜなら、「おすわり」ができることで、他のコマンド(待て、伏せ、おいでなど)のベースになるからです。
行動のスタートを落ち着いた姿勢に切り替えることで、犬の集中力を引き出す効果もあります。

飛びつき防止や落ち着かせる効果
特にトイプードルは喜びを表現するために飛びつくことが多く、来客時や食事前に飛びつき癖が出るケースがあります。
「おすわり」を指示して座らせることで、興奮を抑えることができます。
これは行動心理学でも証明されており、「座る」という姿勢は犬にとって気持ちを落ち着けるトリガーとなるのです。

信頼関係構築にもつながる
「おすわり」ができるようになるということは、飼い主の指示を聞くことができている証拠です。
指示を出し、それに犬が応えることは、信頼関係の基本になります。
この一歩一歩の積み重ねが、しつけの成功を左右するといっても過言ではありません。
トイプードルはいつから「おすわり」を覚えられる?

- 教え始める適切な時期
- 子犬と成犬での違い
- 覚えるまでの平均期間
教え始める適切な時期
一般的には生後2〜3ヶ月頃から「おすわり」を教え始めることが可能です。
この時期は“社会化期”と呼ばれ、人間社会に順応するための学習意欲が最も高まっている時期でもあります。
ただし、無理に覚えさせようとすると逆効果になるため、遊びの延長線で教えるのが理想です。

子犬と成犬での違い
成犬は集中力があるものの、新しいことに対して警戒心を持つ場合があります。
それぞれの特徴を理解してアプローチを変えることが、スムーズなしつけのコツになります。
覚えるまでの平均期間
「おすわり」を習得するまでにかかる期間は平均して1〜2週間程度です。
これは1日1〜2回、5分程度のトレーニングを継続した場合の目安です。
ただし、個体差がありますので、焦らずその子のペースに合わせることが大切です。
「おすわり」の教え方ステップ

- 基本のトレーニング手順
- 成功率を上げるコツ
- ご褒美・タイミングの活用
基本のトレーニング手順
犬が理解するまでのスピードには個体差がありますが、焦らず“遊びの延長”として楽しむこともポイントです。
成功率を上げるコツ
ご褒美・タイミングの活用
褒めるタイミングは「お尻が床についた瞬間」にすること。
遅れると、犬は何を褒められたのかを理解できません。
また、おやつを使う場合も必ず“正しい行動”と結びつけるよう意識しましょう。
タイミングが合えば、1回の成功だけでも大きな学びになります。
トイプードルが「おすわり」できない理由とは?
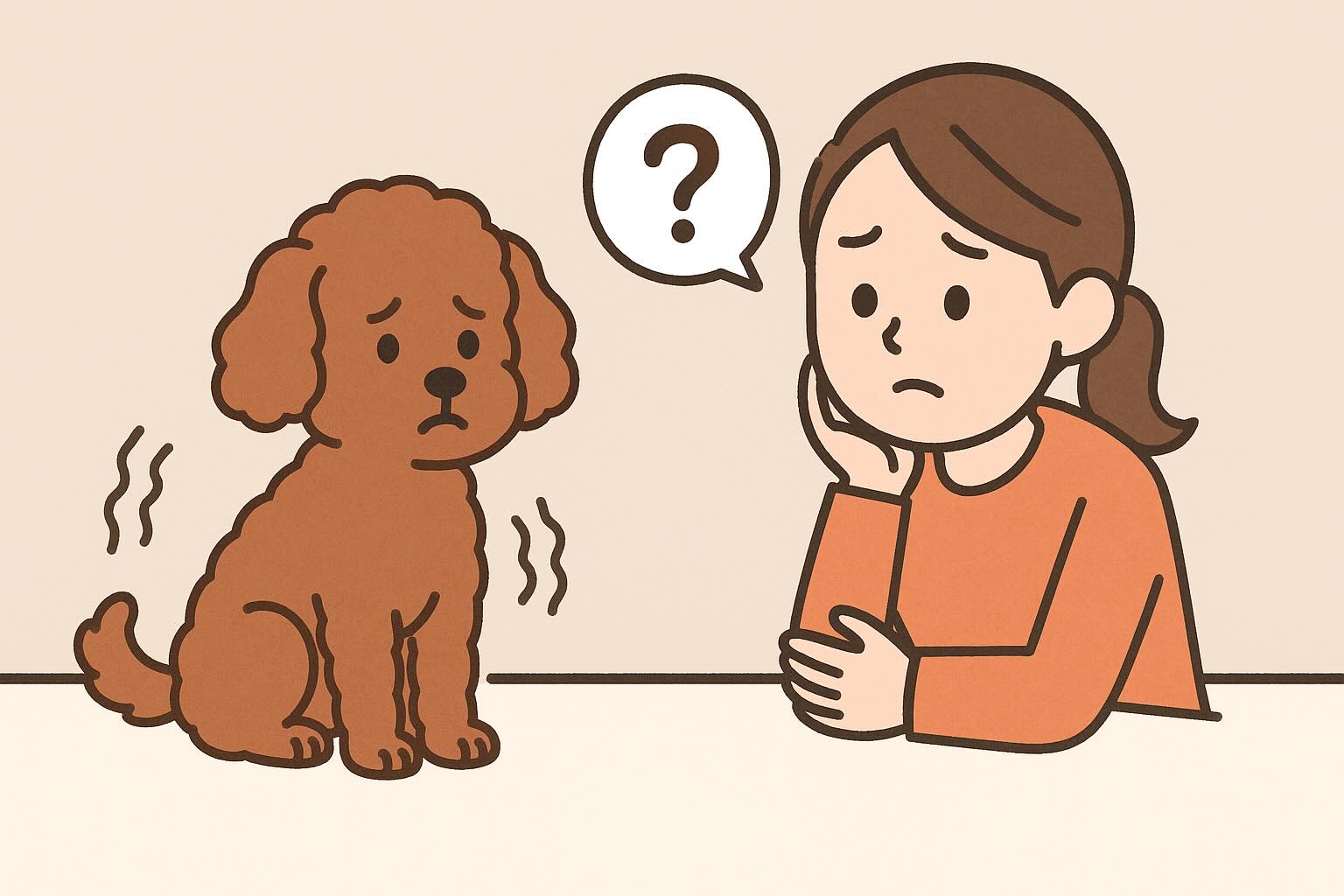
- 環境やストレスによるもの
- コマンドの混乱や誤解
- 骨や関節など病気の可能性
環境やストレスによるもの
トレーニング場所が騒がしい、他の犬や人の存在が気になる、気温が暑すぎるなど、外的環境の影響で集中できないことがあります。
テレビの音や宅配便のインターホンなど、ちょっとした音も敏感に反応する子もいます。
>>トイプードルがテレビに吠える理由とは?原因としつけのコツを徹底解説!
ストレスを感じている場合も同様で、「おすわり」の習得は後回しになってしまいます。
リラックスできる環境を整えることが、学習効率を高める第一歩です。
コマンドの混乱や誤解
家族で指示の出し方が異なっていたり、毎回違う言葉を使っていたりすると、犬が混乱してしまいます。
たとえば、「すわれ」「おすわり」「座って」などが混在すると、犬は区別がつかずに迷ってしまいます。
コマンドは短く、明確に、そして家族全員で統一することが大切です。
骨や関節など病気の可能性
「おすわり」しようとしない、あるいは嫌がる場合は、膝蓋骨脱臼(パテラ)や股関節形成不全などの病気の可能性もあります。
特に後ろ足を不自然に開いた「おかしなおすわり」をしている場合は、早めに獣医師に相談してください。
普段から歩き方や動作に違和感がないか観察しておくことも、早期発見につながります。
「おすわり」が不安定・落ち着かないときの対処法

- じっとできないときの原因
- 飛びつき癖が治らない場合
- 後ろ足の開き方がおかしい場合
じっとできないときの原因
こういったケースでは、短時間で終える、成功した瞬間に褒める、トレーニング環境を見直すといった対応が有効です。
たとえば、静かな部屋で照明や音を調整し、犬が集中しやすい環境を整えることも大切なポイントです。
飛びつき癖が治らない場合
また、興奮を抑えるための呼吸のトレーニング(深呼吸を促すようなテンポで指示を出す)も有効です。
根気よく繰り返すことで、刺激に過剰反応せずに行動を制御できるようになります。

後ろ足の開き方がおかしい場合
特に、成長段階の子犬に多く見られ、発育に関する課題が隠れていることも。
無理に直そうとせず、専門医に診てもらいながらリハビリ的に改善していくのが望ましいです。
よくある失敗とその改善策

- ご褒美が逆効果になることも
- 命令の出し方が曖昧になっている
- 家族内でコマンドが統一されていない
ご褒美が逆効果になることも
毎回大量のおやつを与えていると、それが目的になってしまい、しつけ効果が薄れてしまいます。
おやつは“強化”のために使い、徐々にフェードアウトさせるのがポイントです。
命令の出し方が曖昧になっている
「おすわりして〜」や「座ってくれる?」など、命令形ではなく依頼形だと、犬が混乱してしまうことがあります。
「おすわり」と明確に短く伝えることで、犬も理解しやすくなります。
家族内でコマンドが統一されていない
犬にとってはすべて別のコマンドです。
家族全員が統一した言葉とジェスチャーを使うよう心がけましょう。
「おすわり」しつけを成功させるためのポイントまとめ
- 毎日の積み重ねが大切
- 成功体験を重ねて自信を育てよう
- 一貫性と愛情をもって接する
毎日の積み重ねが大切
トイプードルのしつけは一朝一夕では身につきません。
短時間でもいいので、毎日コツコツ続けることが、確実な習得につながります。
「今日は短くてもいい」「できたらラッキー」くらいの心構えで取り組むと、飼い主のストレスも軽減されます。
成功体験を重ねて自信を育てよう
犬は「できた!」という成功体験から学びます。
できるたびに褒めることで、「またやってみよう!」という意欲が生まれます。
例えば、最初は1秒座れただけでも思いっきり褒めると、「これが正解なんだ!」と理解しやすくなります。
そして少しずつ成功時間を延ばしていくことで、自信を持ってコマンドに応えるようになります。
一貫性と愛情をもって接する
言葉・態度・行動に一貫性を持つこと。
そして、なによりも“愛情”を忘れずに接することが、信頼関係の構築につながります。
しつけは叱ることではなく、教えてあげること。
それを意識するだけで、犬との関係性が大きく変わります。
この記事が、あなたと愛犬の「おすわり」トレーニングに少しでも役立てば幸いです。
焦らず、楽しみながら、一歩一歩前に進んでいきましょう!
しつけの順番に沿って記事を読む場合↓